※本ブログはプロモーションを含んでいます。
管理人のナナコです。
私の娘は今2歳半ですが、今回は私たち家族を襲った不運について書きます。
これから出産する妊婦さん、全員に知ってもらいたくてこの記事を書きました。
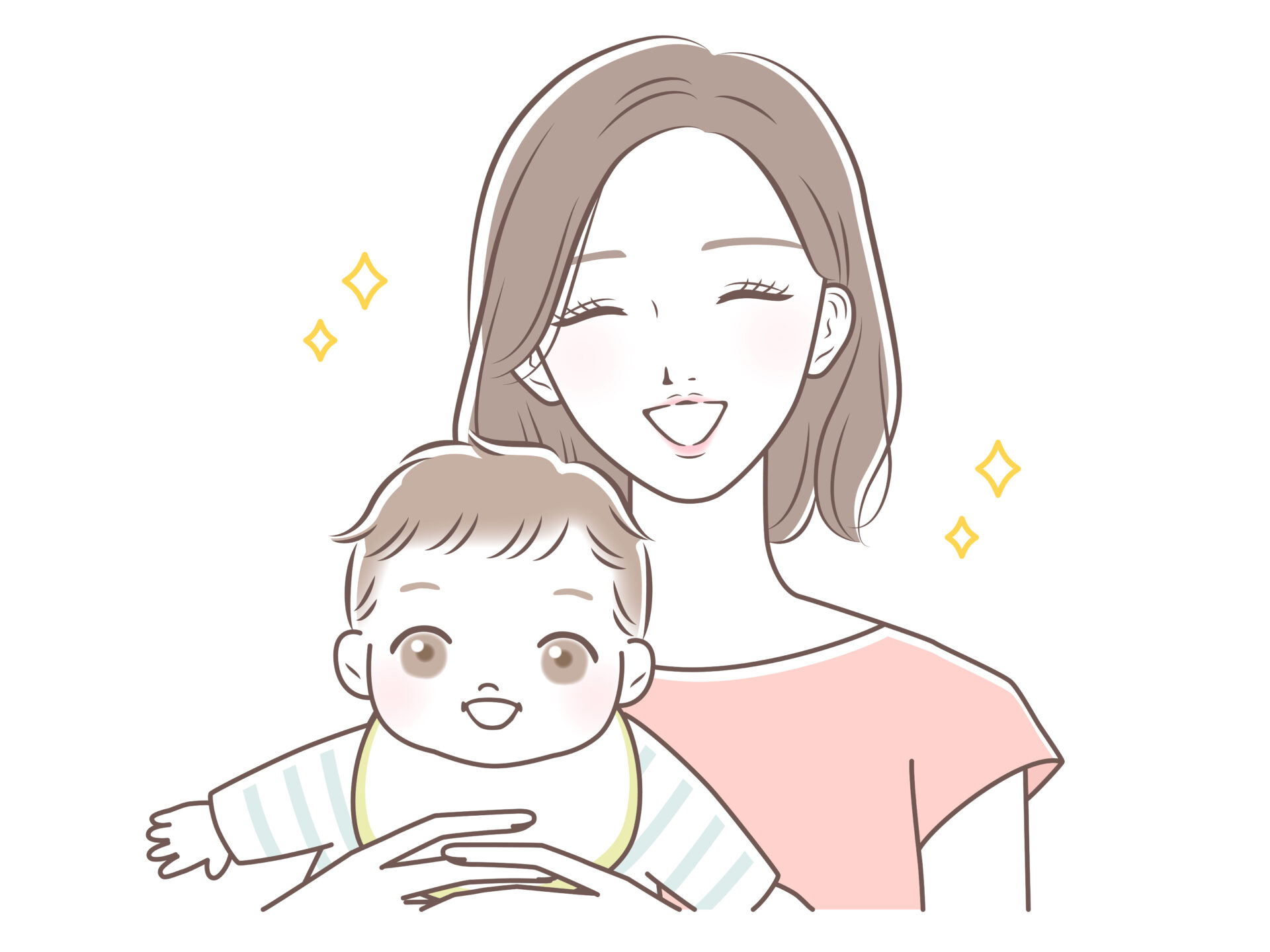
娘の予後のリハビリで使って良かったものや発達にいい影響のあるおもちゃなどは他の記事で紹介しています。
※悲しい出来事を想起させるため、記事は削除する可能性があります。
私の娘に起きた突然の悲劇とその後遺症
私の娘は、元気に生まれ、発達も順調でした。
1歳7ヶ月の頃にはおしゃべり上手で周囲を笑わせるようなひょうきんな女の子に育ち、家族みんながその成長を喜んでいました。
しかし、元気だった娘は突然、高熱を出して痙攣を起こしたことをきっかけに「急性脳症」を発症しました。
昨日まで保育園に行って元気だった娘が、呼吸が止まり、意識を失い、集中治療室に運ばれました。そこから病院で必死に治療を受ける日々が始まりました。
幸い命は助かったものの、脳症による後遺症が残ってしまいました。
娘は現在、言語障害で言葉が全くしゃべれず、多動や睡眠障害もあります。
左右別々にものを操作することが苦手になってしまい、日常生活にも支障が出ています。

完全回復を祈りながらリハビリや通院を続けていますが、より顕著に回復させる方法として「臍帯血保管」も選択のひとつだったのでは、と今となっては思います。
臍帯血とは?なぜ今注目されているのか
臍帯血(さいたいけつ)は、赤ちゃんとお母さんをつなぐへその緒や胎盤に含まれる血液で、再生医療や細胞治療に使われる「幹細胞」が豊富に含まれています。
この幹細胞は、血液疾患や自己免疫疾患、中枢神経系疾患(脳性麻痺など)の治療に活用される可能性があります。
しかも臍帯血は出産時にしか採取できない貴重なものです。
母子ともに痛みやリスクはなく、一生に一度のチャンスです。
>>出産の今だけできる、赤ちゃんのさい帯血保管【ステムセル研究所】
きょうだいで臍帯血を使える可能性
臍帯血は、自分自身だけでなくきょうだい(兄弟姉妹)や家族にも使える可能性があります。
特に遺伝的に近いきょうだい間では移植適合率が高く、白血病や再生不良性貧血などの治療に役立った事例もあります。
私自身、「もし次のきょうだいが授かったら娘に臍帯血を使える状況になるのでは」と考えています。
さらに未来には技術革新によって、高度な治療法が確立される可能性もあります。
そのとき、保管していた臍帯血がその子だけでなく家族の命を守る鍵になるかもしれません。

臍帯血保管の実例:未来への希望
実際、中国では18歳で再生不良性貧血を発症した青年が、生まれた時に保管していた臍帯血で命を救われた事例があります。
この事例を見ると、「まさか自分には関係ない」と思っていても人生は何が起こるかわからない、と痛感します。
臍帯血保管は未来への希望です。「もしも」の時だけでなく、新しい治療法が生まれる可能性にも備えることができます。
臍帯血保管の費用とプラン
日本では民間臍帯血バンクによる保管サービスがあります。費用は10年保管で約27万円~44万円(分割払い可)など、家計に合わせたプランも用意されています。
高額と感じるかもしれませんが、それは「家族全員への未来への投資」です。
突然の病気や事故だけでなく、新しい医療技術への期待も込めて検討する価値があります。
>>臍帯血保管サービスについて詳しくはこちら(ステムセル公式)
まとめ|私からあなたへ伝えたいこと

私自身、「もっと何かできたはず」「自分ごととして真剣に検討すればよかった」と後悔しています。
臍帯血のことは妊娠中、検診時にポスターなどで見ていたはずです。
ですが、検診では一度も引っかからなかったため娘や自分とは関係ないことと当時は思っていました。
急性脳症は、一年間で全国で400~700人の子どもが罹患するという*厚生労働省のデータがあり、確率としては低いのかもしれませんが、我が家では思ってもいない事態が起こってしまいました。
臍帯血が脳症に直接効果があるかどうかは分かりませんが、脳性麻痺の子どもに効果があったという報告もあります。
もし技術革新でさらに高度な治療法が生まれたとき、その臍帯血が役立つ可能性があると、今となっては後悔してなりません。
今、この選択肢を知っているあなたにはぜひ考えてほしい、それが私からの心からの願いです。
・「検診で引っかからなかったから大丈夫」と思っている方へ:人生は予測できません。
・「費用が高い」と感じている方へ:未来への投資として検討してください。大切な子どもと家族のお守りです。
・「まだ迷っている」という方へ:今しかできない選択です。後で後悔してもそのときに戻ることはできません。
どうか後悔しないために、大切な家族への贈り物として臍帯血保管をご検討ください。
>>臍帯血保管サービスについて詳しくはこちら(ステムセル公式)
*引用元:急性脳症の全国実態調査



コメント